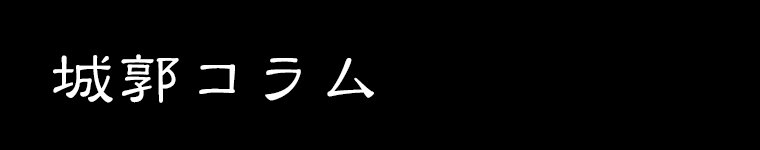投稿日 :
かつて私はサラリーマンをしていた。人と少し違うのは、外資系企業ばかりを何社か渡り歩いたので、自分で起業したいという思いが強かった点くらいである。
そんな私が作家になったのは、たまたま訪れた中世古城がきっかけだった。
その城の名は山中城。箱根山西麓にある小田原北条氏の城である。この城で、北条方は豊臣秀吉の大軍を迎え撃ち、そして壊滅した。それが北条氏の滅亡の序曲となる。
こうした史実を知っている人は多いが、その城の遺構がいかなるものかを知る人は少ない。かくゆう私もそうだった。
2002年5月、たまたま家族旅行で通りかかった山中城に足を踏み入れ、その異形の堀を見て、私は衝撃を受けた。それは類まれな芸術作品だった。
その幾重にも格子が連なったような堀が、北条氏の得意とする「障子堀」という遺構だと知るのは、後になってからだが、この時は、ただその美しさに魅せられた(芝生を張り替えたばかりだった)。


山中城の事をもっと知りたくなり、研究本などを調べていると、戦国時代には「城取り(築城家)」という職業があることを知った。しかも山中城の縄張りを引いたのは、小田原合戦の緒戦となった山中城攻防戦において、最初に討ち死にした間宮康俊という武将だという。
「城取りこそ、自らの作品の中で死ねる唯一の芸術家」というフレーズが浮かんだ。
その時、突然、小説脳が動き出した。
これまでの生涯で、小説家になりたいと思ったことなど一度としてなく、気まぐれに何かを書いたことさえなかった私が、最初の一行を書いた途端、堰を切るように言葉が溢れてきた。
処女作となった『悲雲山中城』(叢文社 廃刊)は、わずか二週間ほどで書き上げた。
それがきっかけとなって中世古城に興味を覚え、執筆活動と並行して城めぐりを始めた。
「作品の発想は、どんな時に浮かぶか」と問われれば、私は「城めぐりをしている時」と答える。これが不思議なのだが、研究本や史料を読んでいても浮かばないアイデアが、フィールドワークをしていると浮かんでくる。
もちろん城に詳しい友人と現地に行き、遺構を見ながら話をすることが、最も効果的である。
友「唐沢山城の佐野氏って、頭を下げてばっかりなんだよね」
伊「へえー、戦わないんだ」
友「こんな立派な城があったっても、めったに戦わないんだよ」
い「どうして」
友「上杉でも北条でも、来た方に頭を下げていれば許してもらえたからだろうね。それにしても、その時、どっちについていたか分からなくなったりして(笑)」
こうした会話から、短編集『城を嚙ませた男』のオープニングを飾る『見えすぎた物見』は生まれた。
尤もこれだけでは、いかに短編でも、小説に仕立てるのは難しい。
ところが唐沢山城には、天狗岩という江戸まで見渡せる絶景のポイントがあり、そこに物見櫓が置かれ、敵の接近を監視していたという話を聞いた。
かくして「物見により敵の接近を知ると、戦わないで頭を下げ続ける戦国国人」というモチーフが浮かんだ。むろん、これでも不十分である。
唐沢山城主の佐野氏のルーツは、平将門征伐で名を成した藤原秀郷である。伝記によると秀郷は、東国でたいへんな評判になっている将門から「味方になってくれないか」と誘われ、悩んでいた。そこで将門に会ってみると、確かに一廉の人物だった。しかし一緒に飯を食った時、飯を飛ばしながら話をするだらしなさに呆れ果て、将門が大を成す人物でないことを見破る。かくして秀郷は将門に与さず、討伐する道を選ぶ。
この逸話は「人の噂に左右されず、自らの目で確かめる」ことの重要性を訴えている。かくしてこの「始祖の家訓」を、モチーフの一つとして使うことにした。
その後、唐沢山城について文献を読んでいた折、佐野氏改易にまつわる逸話に行き当たった。天狗岩から江戸市街まで見渡せることが幕閣に知られた佐野氏は、唐沢山城を廃城にされた挙句、難癖を付けられて改易に処されてしまうのである。
これで、すべてのモチーフがつながった。
「これだ!」という瞬間である。
表テーマは「先々をしっかり見極める」、そして裏テーマとして、「過ぎたるは及ばざるがごとし」という教訓が浮かび上がった。
こうした作劇法に興味のある方は、連作短編集『城を嚙ませた男』所収の『見えすぎた物見』を、ぜひお読みいただきたい。モチーフをつなげて短編を完成させる手法が、よく分かるはずだ。
いずれにしても『見えすぎた物見』は、城に行かなければ生まれなかった話である。
このほかにも、城めぐりをしていてヒントを得たことは山ほどある。下田城から下田湾を見下ろしながら、『鯨のくる城』のアイデアを思いつき、賤ケ岳から余呉湖一帯を眺めることで、佐久間盛政の策略を知り、『毒牙の舞』という作品を書いた。

これらのアイデアは、机にかじりついているだけでは、決して生まれなかったものである。
人はなぜ城跡に魅せられるのか。
誰でも初めは、城といえば天守閣と石垣のある江戸期のものを思い浮かべるはずだ。しかし、その漢字が「土から成る」とある通り、城は土で造られたものが基本である。石材の豊富な西国は別だが、加工しやすく崩れにくいローム層の多い東国では、石垣技術は発達せず、戦国時代には、多くの土の城が造られた。
城数寄は、それら土の城の遺構を見るために、貴重な休日を使って懸命に山に登り、藪をかき分ける。むろんどの城も、たいていは土塁と堀くらいしか残っていない。しかも未整備で分かりにくい上、どこに行っても同じような遺構ばかりである。
城数寄でない方には、何が楽しいのか分からないはずだ。
私も最初はそうだった。しかし一つの城の見学を終えると、なぜかまた別の城に行きたくなる
どうしてそんな気になるのか。城跡の魅力とはどこにあるのだろうか。
私の場合、そこに「人の思考の痕跡」が残っているからである。思考とは、「戦略目標を達成しようとする意思」と言い換えてもいいだろう。
言うまでもなく、城というものは何らかの戦略目標を持って造られる。まず、その場所が選ばれるためには、防衛・侵略拠点、監視、交通遮断、補給基地などの戦略目標がある。
こうした戦略目標を達成するために城は造られる。だがその過程では、試行錯誤が付き物となる。
どのような形状で、どのくらいの規模の堀を穿つのか、または土塁を築くのか、曲輪の形状をどうするのか、どこを掘り切り、どこに竪堀を落とすのか、いかなる場所にキル・ポケットを設けるのか。
城造りというのは、地形・地質から動員力まで種々の制約条件があるため、必ずしも思い通りに行かない。だが、そうした制限をクリアしつつ、目標を達成できる城を築こうとする試行錯誤の痕跡が残っているのに気づくのが、城めぐりの楽しみの一つである。
私は「作家にならなかったら何になっていたか」と問われれば、迷うことなく「築城家」と答えることにしている。もちろんタイムスリップをせねばならないのだが(笑)。